レモンやライムは、アーユルヴェーダの世界では何千年も前から薬として使われてきた植物のひとつです。中でも、日本では手に入りやすいレモンは、日々のセルフケアにぴったりの味方。
今回は、アーユルヴェーダの視点から、レモンのもつ自然のちからと、暮らしの中での活用法をご紹介します。

レモンが持つ自然のちから
レモンは単なるビタミン補給の果物ではありません。アーユルヴェーダでは、レモンは次のような働きを持つとされています。
- 消化力をサポート(アグニを整える)
酸味は消化の火「アグニ」を目覚めさせ、食欲や代謝を整えてくれます。 - やさしいデトックス
朝の「レモン白湯」は、体にたまった老廃物をやさしく排出する助けに。 - 気分をリフレッシュ
レモンの香りには、沈んだ気分をシャキッと明るく整える働きも。
レモンは“薬”としても使える
レモンは果汁だけでなく、皮や種、葉に至るまで、アーユルヴェーダのホームレメディとして幅広く活用されています。
-
ビタミンCが豊富で、免疫力を高める
-
消化促進、血液の浄化、血圧バランスの調整
-
レモンの香りは吐き気を和らげ、果汁は口臭対策にも
-
腎臓の健康サポートにも役立つとされています
レモンは特に、体に重さやだるさを感じる“カパ”が増えている時の調整役にもなります。
レモンの様々な働きを、暮らしの中に取り入れてみましょう。

レモンでできるセルフケア
●スキンケアに
レモン果汁は、肌の洗浄やくすみケアにぴったり。水で薄めてコットンパックにするのもおすすめです。
● お料理に
ドレッシングやサラダ、カレーに。果皮を砂糖漬けにしておけば、スイーツにも活用できます。
● 自然の防腐剤として
カットフルーツの変色防止に、レモン果汁をひとふり。自然の抗酸化作用が働きます。
● お掃除・虫除けに
レモンの皮から抽出されるオイルは、木製家具の艶出しやナチュラルクリーナーに。虫よけスプレーとしても安心して使えます。
レモンに含まれるクエン酸は、ヴァータのバランスを整えるだけでなく、心を落ち着かせる効果や、血圧に良い効果があります。
アーユルヴェーダでは、柑橘系の酸味は神経系のバランスを整えたり、沈静化する効果があると考えられています。ですが、私たちは心を癒したい時には、甘いお菓子や塩辛いスナック菓子を求めてしまいます。是非、レモンの力を活用して下さい。

アーユルヴェーダとレモンの深いつながり
レモンの原産は、ヒマラヤ山脈のふもと。アーユルヴェーダでは、スパイスやハーブの働きをサポートし、消化力を高める“欠かせない食材”として大切にされています。
特に、晩冬から春先はヴァータとカパの影響が混じりやすく、毒素(アーマ)が溜まりやすい時期。そんな季節にこそ、レモンは自然な解毒のサポートになります。
甘いお菓子ではなく、レモンを選ぶという選択
アーユルヴェーダでは、酸っぱいレモンは消化促進を促し、消化力を高めるためにスパイスやハーブの食品の吸収を高めるために使用します。アーユルヴェーダの食事には、欠かせないものです。特に、晩冬から早春にかけて収穫されるレモンは、ヴァータの季節(冬)とカパの季節(春)のアーマ(毒素)の蓄積に対する解毒剤となるでしょう。
気持ちが沈んだ時、私たちはつい甘いものやしょっぱいおやつに手が伸びがち。でも、アーユルヴェーダでは、柑橘の酸味が神経系を整え、心を落ち着かせると考えられています。
そんな時こそ、レモンのさわやかな力を借りてみてください。
自然がくれたレモンのちからを、日々の暮らしに。
小さな果実に宿る大きな恩恵に、今日も感謝を込めて。
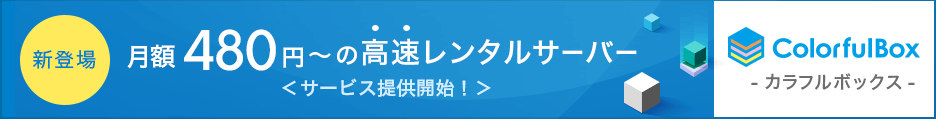



コメント